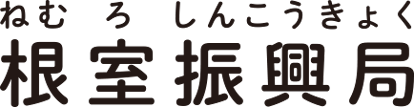択捉島の「自然」について
択捉の蘂取(しべとろ)の夏は、温暖でした。蘂取は、北向きですが後ろに山があり、太平洋側からの冷たい風が入らないので、平坦な岬で構成される根室より暖かかったんです。
木は千島桜が主で春に花が咲く。その頃、山には、ギョウジャニンニクなど色々な軟らかい野草がたくさん生えてくる。春は、野菜代わりに野草を食べていました。村は、煎餅の耳のようなところで、後は全部高い山だった。山の200m位のところまで人が住んでいたが、山の中はクマが多く大変でした。海には、アザラシ、クジラ、シャチがいました。
択捉島での「生活」について
蘂取村は戸数でいくと45戸位でしたが、半分くらいの家では漁業をしていました。後は、学校の先生・役場の職員・郵便局員などでした。
食生活は、米が主食で、副食は魚が主でした。年中、魚がいるわけではなく季節に合わせて、サケ・マスが捕れるときにはサケ・マスを食べていました。釣れる魚は根室と同じでオヒョウ・アイナメが釣れたのでおかずにしていました。
小学生の頃は、冬はスキー。周りが山ばかりなのでとてもよかった。
ソリは、山が急なのでやれなかった。スキーは、みんなが持っていて上手でした。
スケートは、50年以上も前には、リンクがなかったのでやっていなかった。
サケ・マスが捕れ出すと魚が遊び道具になりました。魚を追い回してとっていました。男の子は、弓を作ったり野原を走ったり外で遊んでいました。
女の子は家の中でお手玉や竹わりをやっていました。
百人一首が流行っていました。ランプだったので、夜は暗くてできない。昼間どこかの家に集まってやっていました。
一番思い出に残っていることは、釣るにしろ追いかけて採るにしても、季節的にいっぱいいたサケ・マスとの戦い。子供の時だから戦いだった。たくさんの川があり、ちょっと奥に入るとヤマメ等たくさん釣れたけど、あまり奥に入るとクマがいるので、変な所には行けませんでした。ただ、クマがこれない、魚釣りができる所はよく釣れた。海は、アブラコのポイントに行って釣っていたことが印象に残っています。
「現島民との交流」について
ロシアとの関係をちゃんとしていくには、交流をはずすわけにはいきません。交流を通じて気持ちを分かってもらうことが重要です。そして当時、私達日本人がどのように生活をしていて、戦後になってから占領してきたソ連軍とソ連人にどんなことをされたか分かってもらわなくては、ロシア人との真の意味での交流は難しいと思っています。
自分たちが追い出されたから、ロシア人も追い出すのではなく、一緒に住めるのなら一緒に住める方法を考えていかなくてはなりません。
お互い言葉を知らない状況で、一緒に住むことは大変なので、言葉の問題を解決する必要があると考えています。特に、小・中・高校生など若い人達が、語学をちゃんとやってから共存等を考える必要があると思います。