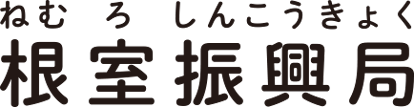繁殖管理方法の再チェック
繁殖は酪農経営の要です。昨夏は暑さの影響から、その日に消耗した体力を十分に回復させることができず、繁殖サイクルが大きく崩れた個体もいることと思います。
安定した生産サイクルを整えるための基本管理方法について再チェックしてみましょう!
1.発情発見の重要性
繁殖成績を高めるためには、発情発見率が重要です。
根室管内の発情発見率と分娩間隔の関係を見ると、発情発見率が低い牧場ほど分娩間隔が長期化しているのがわかります(図1)。
そこで、次項では発情発見からその後の対処のポイントについて紹介します。
図1 発情発見率と分娩間隔(2016乳検成績)
2.繁殖管理方法~発情発見から受胎するまで~
1. 発情発見
(1) 発情観察
発情発見率は観察回数が多く、観察時間が長いほど高まります。また、発情徴候は夜中から早朝にかけて示す傾向があります(表1)。牛舎作業中の観察の他、夜や朝作業前の見回りなど、農場の作業性を考慮しながら、発情観察の「回数・時間・タイミング」を検討しましょう。
表1 24時間中の発情の分布
(2) 授精適期
授精のタイミングはスタンディング発情が終わる頃から排卵されるまでの間が最適とされ、発情開始から約半日後になります。そのためAM・PM法(表2)を活用することで、牛が適期で授精を迎えることができます。
表2 AM・PM法
2. 伝達
人工授精に立ち会い、人工授精師に牛の状態を伝えることで繁殖障害などの個体に対して早期の対応が可能になります。
3. 授精後の対応
妊娠関連糖タンパク(PAGs)検査により、人工授精後28日目以降の牛の妊娠の有無が分かります。授精後早期に不受胎牛を見つけることで、牛群の空胎日数の短縮に繋がります。