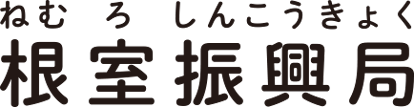「春の草地管理のポイント」
1. 春耕期予報
気象庁の長期予報(1月23日発表)によると、これから先3ヶ月間の傾向として、気温は平年並~高い傾向80%、降水(雪)量は平年並となっています(図1)。平年に比べ今年は融雪が早まる可能性があります。
図1 気象庁発表による春耕期予報(気象庁HPより)
2. 施肥時期のポイント
根室管内の主体であるチモシー主体草地の場合、融雪後の施肥時期が早いほど有穂茎数が多く、収量性も高くなります(図2)。
「萌芽期」の平年値は根室管内南部で4月20日、同北部で4月25日ですが、今後の気象経過によっては早まることが予想されます。
萌芽期のめやすとしては、ほ場全体の4~5割で新芽が出て草地全体にうっすらと新緑が見られるタイミングです。意識的にほ場観察し、適期施肥に備えましょう。
図2 早春の施肥時期がチモシー1番草乾物収量に及ぼす影響(根釧農試、1986)
3. 放牧開始の時期は
冬季間舎飼いしていた搾乳牛を放牧地に出す際には「慣らし運転」が必要です。成牛の場合、ルーメン微生物が放牧草に対応できるまでに10日程度必要とされています。放牧開始時期を早めることで放牧馴致ができ、スプリングフラッシュへの対応にもなることから、放牧地の草丈が10cm程度(5月上旬頃)になったら早めに放牧できるよう準備しましょう。
4. 越年草対策
昨年は秋まで高温が続いたことから、最終番草刈取後に牧草が伸長したほ場が多いと思われます。ほ場の茎葉残さと雪の有無を比較した調査では、雪と茎葉残さがある場合は地温が保持され、気温の影響を受けづらいことが分かります(図3)。そのため越冬性の低い草種を利用する場合は刈り残すことがプラスの効果につながることも考えられます。
図3 地温に及ぼす雪と茎葉残さの影響
一方で、翌年の一番草サイレージの不良発酵など品質への影響も懸念されます。温暖化の影響により今後も同様の傾向が想定されることから、将来的に以下のような対応が必要となる可能性があります。
3番草の収穫(原物収量0.7t/10a以下だと経済的合理性が低い)または掃除刈りの実施
草地更新の際にチモシー中生品種(2回収穫を想定)またはオーチャードグラス、アルファルファ等の導入検討(3回収穫を想定)
各農場の自給飼料畑面積や収穫体系、飼料給与形態等に合わせた経営者判断が求められます。