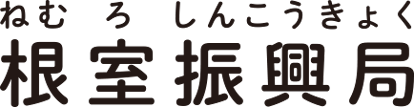チーズの出来栄えを判定できる力を身につけよう!
手作りチーズの魅力は「自分の牧場で搾った牛乳でおいしいチーズを作って食べる」ことにあります。
でも、せっかく作ったチーズが、「熟成中に膨らんだ」「苦みがある」「異臭がする」など、「これって食べても大丈夫?」と不安になるような状況になることもあります。そのような時は、もったいないようですが食べない事、そして、食べられなくなった原因を考え、次は失敗しないようにすることが大切です。
安全でおいしいチーズを作り、食べ続けていくためには、チーズの出来栄えを判定できる力を身につけることが必要です。
また、色々なチーズを食べてみて本来の味がどのようなものかを確認しておくことも大切です。
1.種類別に見るチーズの欠陥とその原因
ここではカッテージ・ゴーダ・ストリングについてのチーズの欠陥とその原因について記載しますが、その他のチーズにも共通する点がありますので、参考にして下さい。
チーズの種類
カッテージチーズ
欠陥部分
風味の欠陥:酸味臭・発酵臭・飼料臭
考えられる原因
- 原料乳に問題がある。
- ホエー排除が不十分である。
- 冷蔵庫へ入れる前の冷却が不十分だった。
- 保存温度が5℃以上あった。
- 器具の殺菌・滅菌が不十分だった。
チーズの種類
ゴーダ
欠陥部分
苦みが強い
- 原料乳の殺菌温度が高すぎた。
- 原料乳のpHが低かった。
- レンネットの添加量が多すぎた。
- 食塩添加量が少なかった。
- 熟成温度が高いと苦みを生じやすい。
チーズがふくらんだ
- 酪酸菌による酪酸発酵(熟成2~3ヶ月)
- 大腸菌によるガス膨張(熟成1週間以内)
組織がもろい
- スターターの品質や量の違いで過度に酸生成した。
- セッティング時間が長すぎた。
チーズの種類
ストリング
欠陥部分
チーズの表面がヌルヌルする
- 塩水のpHがチーズのpHとあっていない。
- 塩水に乳酸を数滴添加する、ホエーを混ぜるなどでpHを調整すると良い。
チーズの表面がブツブツと粗くなる
- マッティングの時間が長すぎて、pHが下がりすぎてしまった。
- ストレッチテストをこまめに行い適時にストレッチングを行う。
2.細菌汚染されたチーズの特徴
細菌汚染されたチーズは嗜好性が悪くなるばかりでなく、健康を害する場合もあります。細菌汚染を防ぐためには、「良質の原料乳」「原料乳の殺菌」「二次汚染の防止」を心掛けることが大切です。主な汚染菌の特徴と対策を示しましたので、参考にして下さい。
汚染菌
大腸菌
細菌の特徴
人や哺乳動物等の腸内に常住し、糞便中に絶えず排出される。
飲料水や飲食物から検出された場合、排泄物で汚染されている証拠である。
細菌汚染されたチーズの特徴
熟成のごく初期段階で発生。見た目も臭いも醜悪で、強い酸味がある。
内部がスポンジ状になる。
対策
原料乳は殺菌する。
二次汚染防止のため、清潔な場所で製造する。手洗い、器具の洗浄・消毒等を徹底する。
汚染菌
黄色ブドウ球菌
細菌の特徴
代表的な化膿菌であり、エンテロトキシンという毒素を出す食中毒の原因菌でもある。
細菌汚染されたチーズの特徴
カットすると切断面に粘液が出る。
対策
大腸菌と同様。
汚染菌
リステリア菌
細菌の特徴
家畜全般・土壌などいろんな環境に存在し、37℃前後で良く生育する。
リステリア菌を原因とする食中毒では死亡に至ることもあり、特に妊産婦・乳幼児・免疫が落ちている人や高齢者等は注意が必要。
細菌汚染されたチーズの特徴
チーズの出来に影響しないので判定できない。
対策
大腸菌と同様。
チーズの出来に影響しない分、より衛生面に注意が必要。
汚染菌
酪酸菌
細菌の特徴
土壌菌の1つでチーズ中の乳酸から酪酸と水素ガスを生成する。
内生胞子という熱に強い形でも存在するので、チーズづくりに用いられる低温殺菌では死滅しない。
細菌汚染されたチーズの特徴
異常なガスホールができ、ひどいときには破裂する。酪酸臭がする。
対策
牛乳を汚染する原因がサイレージ由来なので、原料乳の品質管理が重要。
やむを得ない場合は、硝酸塩や塩化リゾチームなど異常発酵を抑えるものを添加する方法がある。
チーズ作りの一口メモ
「作ったチーズが柔らかすぎたのは、プレスが足りなかったから?」
こんな声が良く聞かれます。
でも実際はプレスよりも、次の事項がチーズの水分を左右しています。
- レンネットの量 (多いと低水分)
- 牛乳の乳酸発酵度 (高いと低水分)
- カードの大きさ (小さいと低水分)
- クッキング温度 (高いと低水分)
- 撹拌時間 (長いと低水分)